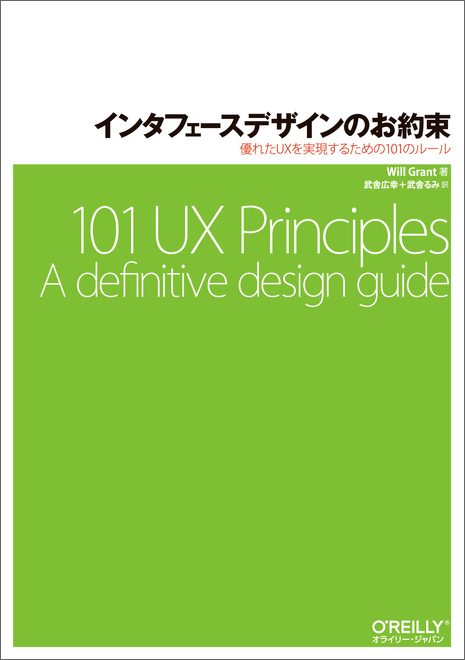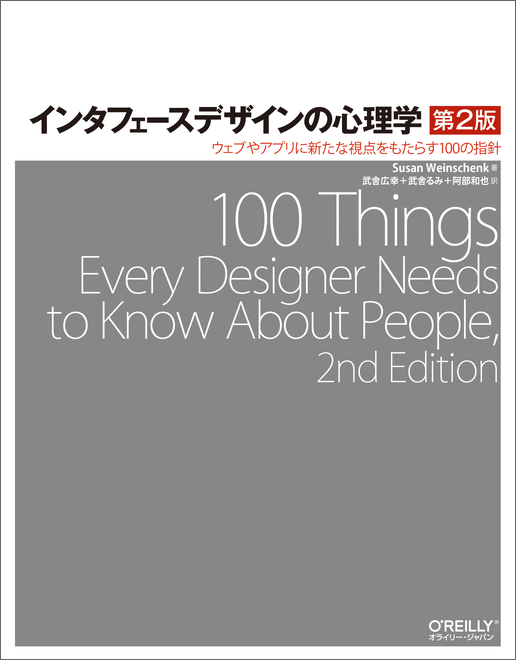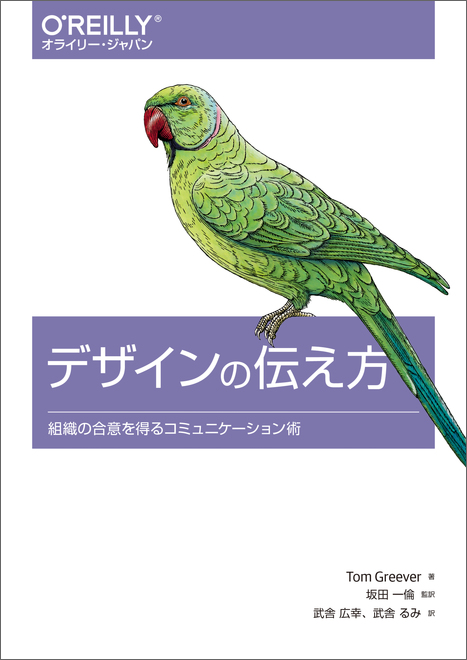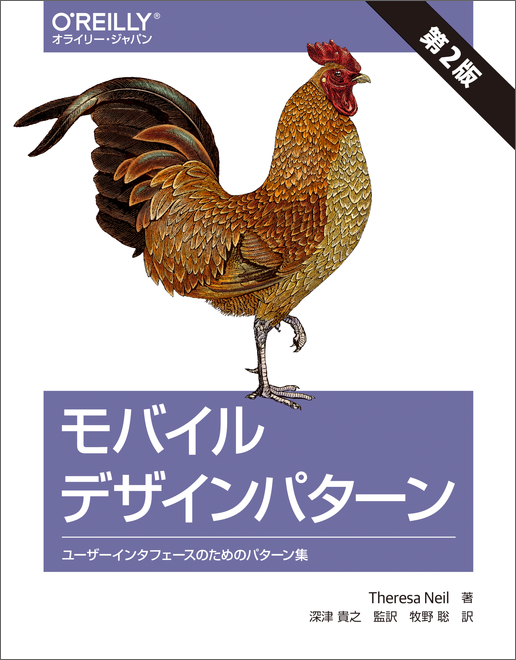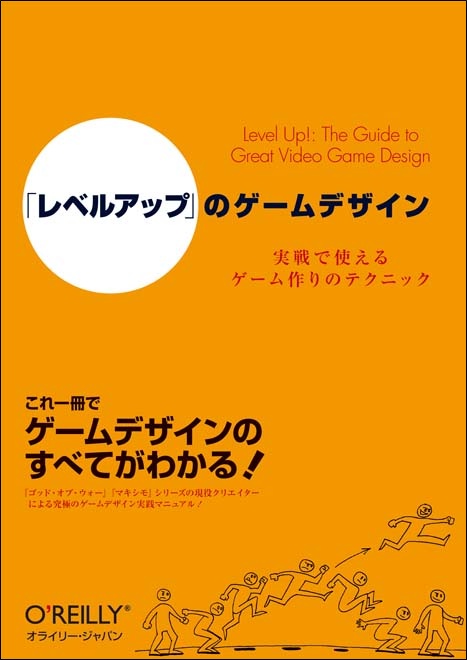ベストセラー書『インタフェースデザインの心理学』の続編。本書では、デザイナーが心に留めておくべき指針を、最新の研究で明らかになった事実とともに紹介します。「画面上の情報を読むのと本を読むのとでは読み方が違う」「読むというのは生得の能力ではない」「意識より無意識のほうがビッグデータの処理に長けている」「中心視の対象は周辺視野が決めている」「中高年の人々が科学技術を使いこなすのに手間取る理由は、記憶力が衰えたからではなく記憶力に自信がなくなったからである」「視力のない人は舌にカメラを接続すれば見れる」……このほかにも94の指針を収録。驚くべき「新たな100の指針」をお楽しみください。
翻訳者によるサポートページ(正誤表)。
続・インタフェースデザインの心理学
―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす+100の指針
Susan Weinschenk 著、武舎 広幸、武舎 るみ、阿部 和也 訳
![[cover photo]](https://www.oreilly.co.jp/books/images/picture_large978-4-87311-771-3.jpeg)
- TOPICS
- Design
- 発行年月日
- 2016年08月
- PRINT LENGTH
- 320
- ISBN
- 978-4-87311-771-3
- 原書
- 100 MORE Things Every Designer Needs to Know About People
- FORMAT
目次
これからのデザイナーは行動科学者たるべし
1章 人はどう見るか
001 人は曲線を好む
002 人は左右対称を好む
003 過剰な錐体細胞
004 中心視野で見るべきものは周辺視野で決めている
005 周辺視野は危険を見て取り、感情に関わる情報を中心視野より素早く処理する
006 周辺視野は低解像度画像のようなもの
007 感情と視線の戦いでは感情が勝利する
008 見つめることが逆効果になる場合も
009 デザインの良し悪しの判断は瞬時に下される
2章 人はどう考え記憶するか
010 人は2種類の思考を使っている
011 記憶は容易に変わり得る
012 反復により強化される記憶もある
013 音楽は記憶とともに感情やその場の雰囲気も呼び起こす
3章 人はどう決めるか
014 人はシステム1の思考で決めてしまう
015 人はもっとも輝いているものを選ぶ
016 複雑な決定をしなければならないときはフィーリングに従う
017 難しい判断をしようとしているときには瞳孔が拡大する
018 自信が決断の引き金になる
019 意思決定に対するストレスの驚くべき影響
020 人は特定の時期に意思決定する
021 人は特定の記憶に従って決断する
022 脳の活動を見れば決定が予言できる
4章 人はどう情報を読み理解するか
023 読みにくい文章のほうが学習効果が上がる
024 動詞より名詞のほうが人を動かす
025 同音異義語は行動のきっかけとなり得る
026 人はオンラインでは記事の6割しか読まない
027 オンラインでの「読み」は通常の「読み」と違うものか?
028 読む行為で重要なのは紙の本での多感覚な体験
029 「古い」メディアを脱却する時は来ている
5章 人は物語にどう影響されるか
030 物語で活性化する脳
031 ピラミッド構造の物語は脳内物質の濃度に影響を与える
032 物語に備わっている「注目を集める力」
033 言動を大きく左右するセルフストーリー
034 セルフストーリーを変えるなら「小さな一歩」から
035 「公言」でセルフストーリーが強化
036 ストーリーを変えると言動が変わる
6章 人は他人や技術とどう関わり合うか
037 感情は伝染する
038 人は動画広告を嫌う
039 楽しく驚くような動画広告は目を引く
040 情報を広めたいと思わせる感情は「ショック」ではなく「驚き」
041 オキシトシンは「絆ホルモン」
042 絆があれば熱意が増す
043 警告機能のあるデバイスは認知能力を低下させる
044 携帯電話が近くにあると一対一の人間関係にマイナスの影響が
045 人は人間の特徴をある程度付与された機械を信頼する
046 人が機械に感情移入することもある
7章 創造性はデザインにどう影響するか
047 誰でもクリエイティブになれる
048 創造性の第一歩は「実行注意ネットワーク」の活性化から
049 クリエイティブになるためには「デフォルト・モード・ネットワーク」を活性化させる
050 「アハ体験」を促す
051 白昼夢が創造性を高める
052 睡眠が創造性を高める
053 雑音や音楽が創造性を高める
054 ある程度の制約があるほうがクリエイティブになれる
055 適度な共同作業が創造性を高める
056 完璧主義がクリエイティブな活動を妨げることもある
8章 人体はデザインにどう影響するか
057 人は脳だけでなく身体でも考え、感じる
058 人は無意識にジェスチャーをする
059 人の動作は身体的制約を受ける
060 親指の届く範囲
061 ユーザーと画面の距離は重要
9章 人はものをどう選び買うか
062 人はオンラインショッピングと店舗でのショッピングを切り離しては考えない
063 現金払いだと使用金額が減る
064 人は認知的不協和が原因で買ったものに執着する
065 人は認知的不協和が原因でものを買う
066 人は数字に影響される
067 オンラインショッピングは期待を高める
10章 世代、地域、性別はデザインにどう影響するか
068 誰もがニュースのチェックや重要な用事にスマートフォンを使う
069 スマートフォン利用の世代差はタスクによって異なる
070 タスクが5分以内で済む場合、人はスマートフォンを使う
071 「携帯電話の所有者=スマートフォンの所有者」とはかぎらない
072 女性がインターネットにアクセスできない国は多い
073 ゲーマーには世代差も性差もない
074 人の目に何が魅力的と映るかは年齢、性別、地域で異なる
075 人が望む選択肢の数は加齢で減少
076 「オンライン」と「オフライン」のメンタルモデルには世代差が
077 米国では65歳以上の半数以上がネットユーザー
078 40歳を過ぎると老眼に
079 加齢とともに見分けづらくなる青色
080 65歳以上では1億人近くの聴力に問題が
081 運動技能は60代半ばまで衰えない
082 高齢者はセキュリティーのための質問に答えられない場合も
083 人は加齢とともに記憶力への自信を失う
084 2020年には全消費者の40%がZ世代に
085 1歳児の1/3以上はタッチスクリーンが使える
086 幼児は笑っているときのほうが学ぶ
11章 人はインタフェースやデバイスとどうやり取りするか
087 動画の「流し見」を可能にするダイジェスト
088 カルーセルは嫌われ者ではない
089 人はスクロールをする
090 運転中は車に話しかけることもやめたほうがよい
091 「ゲーミフィケーション」を用いたほうが人を引きつけられるとは限らない
092 ゲームには知覚学習を強化する効果がある
093 選択肢は少なく
094 人は健康管理デバイスを欲する
095 体調を監視/調整する埋め込み型デバイスの需要は増えそう
096 人は自分の脳でテクノロジーをコントロールできる
097 人はマルチモーダル・インタフェースに適応する
098 人は複合現実を受け入れる
099 6億4,500万超の人に視覚障害や聴覚障害がある
100 人は感覚データを無意識に処理している
訳者あとがき
参考資料
索引