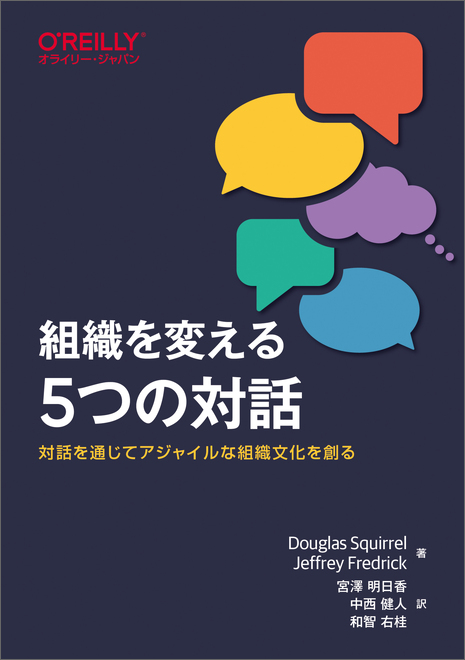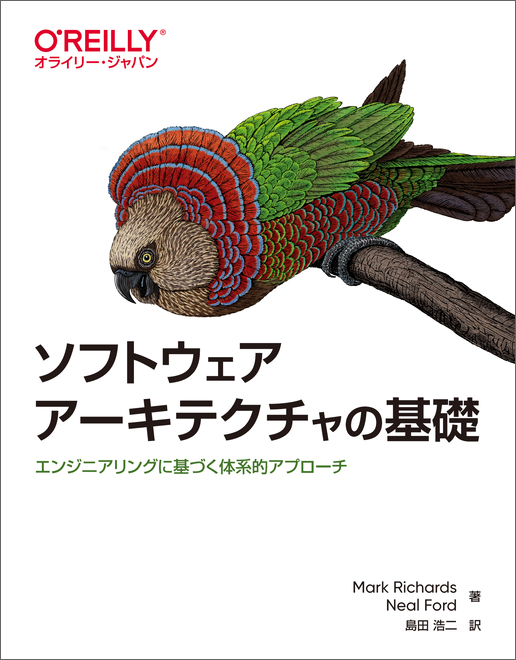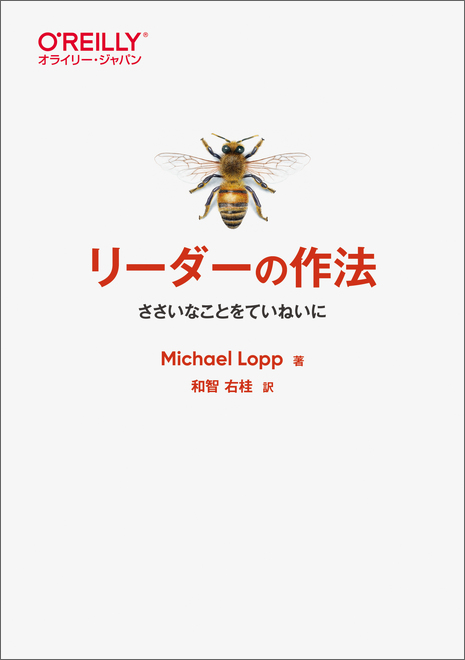優れたアイデアやデザインがあっても、それだけではソフトウェアプロジェクトを成功させることはできません。プロジェクトを円滑に進めるためには、ステークホルダーの理解と支持を得て、チームが協力できる環境を作ることが重要です。本書では、そのために不可欠で効果的なコミュニケーションの方法を解説します。具体的な例やパターンを通じて、適切にメッセージを伝えるためのドキュメントや図の作成方法を紹介します。
まず、ソフトウェアアーキテクチャの視覚表現を活用し、受け手にわかりやすくメッセージを伝える方法を解説します。次に、書面・口頭・非言語コミュニケーションの技法を用いて、相手に意図が正しく伝わるように工夫する方法を紹介します。また、ナレッジマネジメントを強化し、チームや組織の集合的な知識を最適化することで、生産性と革新性を向上させる手法についても解説します。さらに、アーキテクチャに関する重要な意思決定を的確に記録し、関係者と共有する方法を学びます。そして、リモートやハイブリッド環境において、同期・非同期の手法を適切に使い分けながら、円滑に連携するためのアプローチについても詳しく説明します。
開発者とアーキテクトのためのコミュニケーションガイド
―パターンで学ぶ情報伝達術
Jacqui Read 著、宮澤 明日香、中西 健人、和智 右桂 訳
![[cover photo]](https://www.oreilly.co.jp/books/images/picture_large978-4-8144-0105-5.jpeg)
- TOPICS
- Business/Essay
- 発行年月日
- 2025年05月
- PRINT LENGTH
- 296
- ISBN
- 978-4-8144-0105-5
- 原書
- Communication Patterns
- FORMAT
- Print PDF EPUB
関連ファイル
目次
推薦のことば
はじめに
第I部 視覚的コミュニケーション
1章 コミュニケーションの基礎
1.1 相手を知る
1.2 抽象度の混在
1.3 表現の一貫性
1.4 まとめ
2章 ごちゃごちゃをすっきりと
2.1 色の使いすぎ
2.2 多重の入れ子
2.3 関係性のクモの巣
2.4 テキストのバランス
2.5 まとめ
3章 アクセシビリティ
3.1 色に頼る
コントラスト
色覚障がいのためのデザインツール
3.2 凡例を含める
3.3 適切なラベル付け
3.4 まとめ
4章 ナラティブ
4.1 まずは概要から
データフロー図
4.2 図の流れを想定通りにする
4.3 明確な関連
関連の種類
4.4 まとめ
5章 表記法
5.1 アイコンに意味を託す
5.2 UML はUML のために使う
5.3 ふるまいと構造の混在
単一責任の原則
5.4 想定を裏切る
5.5 まとめ
6章 構成
6.1 分かりづらい図
6.2 スタイルが伝えるもの
例:質よりスタイル
6.3 誤解を招く構図
6.4 視覚的なバランスを作る
6.5 まとめ
第II部 マルチモーダル・コミュニケーション
7章 文章コミュニケーション
7.1 言葉はシンプルに
神経多様性
7.2 頭字語地獄
知識の呪い
さまざまな意味
7.3 構造化された書き方
7.4 技術文書の構文
7.4.1 強い動詞
7.4.2 短い文
7.4.3 精緻な段落
7.4.4 一貫した語彙
7.4.5 受け手への共感
技術文書のためのアドバイス
7.5 まとめ
8章 言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション
8.1 メッセージのエンコード
8.1.1 反応の予見の活用
8.1.2 目の前の相手に集中する
8.1.3 ボディランゲージとジェスチャーを使う
8.2 メッセージのデコード
8.2.1 バイアスとの闘い
例:ジーノは異論を歓迎する
8.2.2 当事者意識を持つこと
8.2.3 文化の違いを認識する
8.3 影響と説得
8.4 まとめ
9章 レトリックの三角形
9.1 エートス
9.1.1 資格の確立
例:ポリグロット・メディアで信頼を構築する
9.1.2 信頼できる情報源を使う
9.1.3 自己開示をする
バイアスと利益相反
9.1.4 知識を示す
9.2 パトス
9.2.1 ストーリーを語る
例:ポリグロットメディアにおける教訓
9.2.2 心から話す
9.2.3 生き生きとした言葉と強力なイメージを使う
隠喩、直喩、アナロジー
9.3 ロゴス
9.3.1 データと事実を使用する
9.3.2 論理的なつながりを作ること
9.3.3 論理的思考と論証の活用
9.4 まとめ
第III部 ナレッジを伝達する
10章 ナレッジマネジメントの原則
10.1 プロジェクトよりもプロダクトを重視する
10.1.1 プロジェクト志向
10.1.2 プロダクト志向
10.2 テキストより抽象イメージ
10.2.1 箇条書き
10.2.2 表
10.2.3 視覚的抽象化
10.2.4 ワードクラウド
10.2.5 チャート、グラフ、図
10.2.6 その他の抽象化
10.3 パースペクティブ駆動ドキュメンテーション
パースペクティブを定義する方法
10.3.1 パースペクティブもDRY
10.3.2 フラクタル・パースペクティブ
図のレイヤ化
10.3.3 パースペクティブを実装する
アーキテクチャにおけるパースペクティブとビュー
10.4 まとめ
11章 ナレッジと人
11.1 早期かつ頻繁にフィードバックを得る
埋没費用の誤謬
例:フィードバックはプロセスの一部である
11.2 負担の共有
11.2.1 オープンなフォーマット
オープンなフォーマット
11.2.2 アクセシビリティ
11.2.3 コラボレーション
11.2.4 役割と責任
11.2.5 さらなるテクニック
11.3 ジャストインタイムアーキテクチャ
なぜ決定を後回しにするのか?
11.4 まとめ
12章 効果的なプラクティス
12.1 アーキテクチャ決定記録(ADR)
どのような決定にADR が必要か?
12.1.1 ADR の構造
12.1.2 ADR の内容
12.1.3 ADR の保管場所
12.1.4 ADR の組織文化
意思決定に関する神話
12.2 アーキテクチャ特性
アーキテクチャ特性リストの例
12.3 ドキュメント・アズ・コード
12.3.1 技術文書
12.3.2 自動生成ドキュメント
12.3.3 その他のドキュメント
ドキュメント・アズ・コードのためのオープンソースツール
12.4 まとめ
第IV部 リモートでのコミュニケーション
13章 リモート・タイム
13.1 時間を同期する
13.1.1 タイムゾーン
13.1.2 共感と妥協
13.1.3 分割シフト
日光節約時間(DST)/サマータイム
13.2 勤務パターンを尊重する
13.2.1 対応可能な時間を伝える
13.2.2 パートタイムの勤務時間を守る
13.2.3 休日の計画
祝日と行事
13.2.4 地理と文化を考慮する
労働と異文化
13.2.5 実際の労働能力を認識する
効率的に会議を予約する
13.3 集中力と生産性の向上
13.3.1 通知の管理
13.3.2 タスクの自動化
13.3.3 相手のリズムに合わせて働くこと
13.3.4 集中力のリズムに合わせたスケジュール設定
フォーカスタイムを伝える
13.4 まとめ
14章 リモートの原則
14.1 同期のためのミーティング
14.1.1 同期か非同期か
例:ポリグロット・メディアにおける同期ミーティングの見直し
14.1.2 ミーティングの改善
同期的なミーティングの削減
なぜZoom 疲れになるのか?
14.2 非同期な思考
14.2.1 非同期の利点
14.2.2 非同期コミュニケーションの障壁
14.2.3 方向性が重要
14.2.4 非同期の方法
14.2.5 非同期コミュニケーションの強化
非同期コミュニケーションの期待値を設定し、対応する方法
14.3 リモートファーストの働き方
14.3.1 リモートファーストvs リモートフレンドリー
14.3.2 リモートファーストのメリット
14.3.3 リモートファーストへの進化
14.4 まとめ
15章 リモートチャネル
15.1 対等なメール
15.1.1 メールの利用目的
15.1.2 メールに対する期待値
15.1.3 メールはわかりやすく
15.1.4 メールのコツ
機械的な言葉遣いを避ける
15.2 オンラインプレゼンテーション
15.2.1 受け手を巻き込む
15.2.2 プレゼンテーションの内容
スライドデッキvs スライドメントvs インフォデッキ
15.2.3 スクリーンシェア
15.3 リモートツールとガバナンス
15.3.1 選定のテクニック
例:文化的適合性を考慮する
15.3.2 リモートツール
15.3.3 データの氾濫
15.3.4 セキュリティ
15.3.5 ツールの効率
15.3.6 ツールガバナンス
15.4 まとめ
16章 エピローグ
付録A ADR テンプレート
訳者あとがき
索引