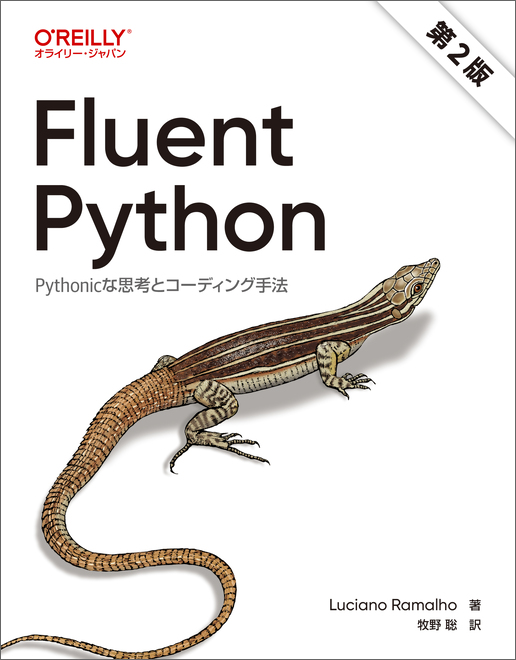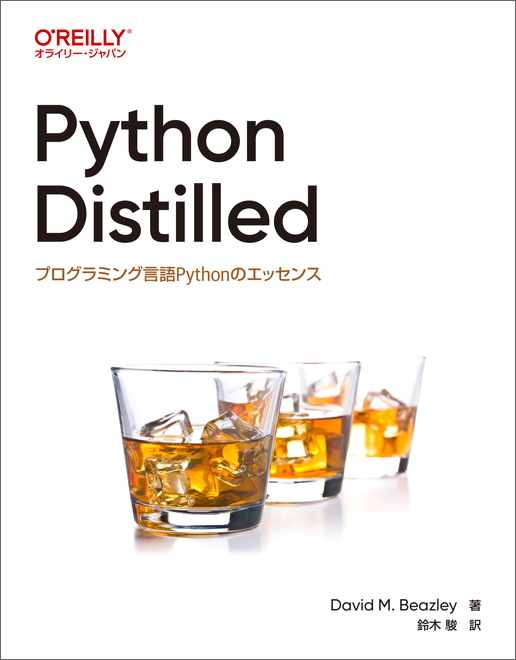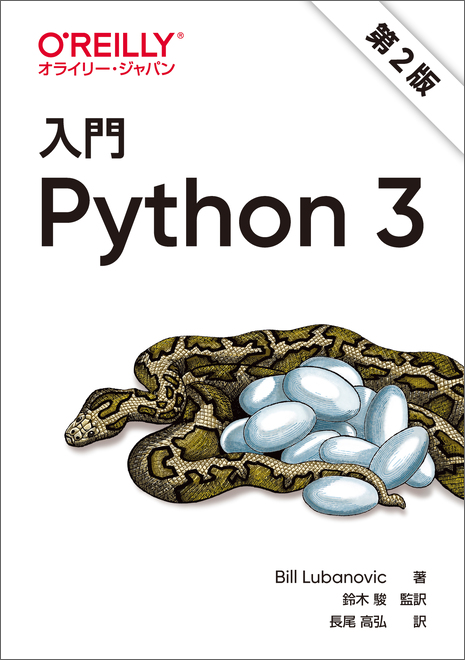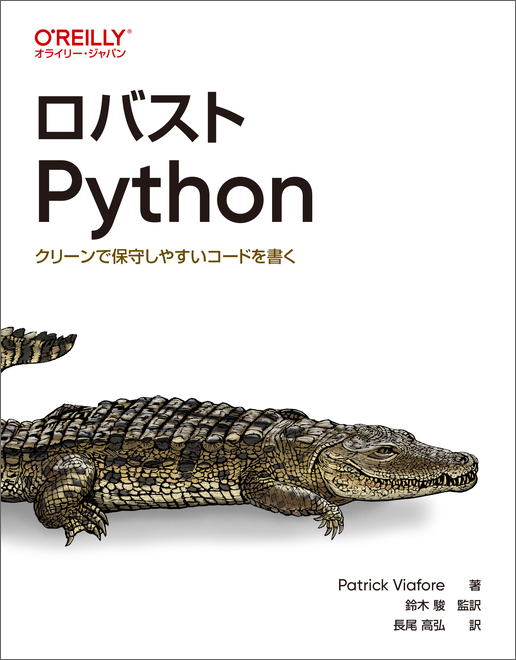GoogleでPythonを使ったさまざまなサービスを立ち上げ、Pythonを知り尽くした著者による、Pythonエキスパート必携書の最新版です。第3版では、Python 3.13までの最新機能に対応し、第2版から新たに35項目を追加し、既存項目も時代に合わせて大幅に改訂されています。各項目では、優れたPythonコードを書くために何をすべきか、何を避けるべきか、そしてその理由をPythonの流儀に従って明確に解説。効率的でロバストであるだけでなく、読みやすく、保守しやすく、改善しやすいPythonicなコードを書く秘訣を学べます。Web開発、データ分析、自動化スクリプト、AI訓練まで、あらゆる分野でPythonの真の力を発揮したい開発者にとって、必読の一冊です。
Effective Python 第3版
―Pythonプログラムを改良する125項目
Brett Slatkin 著、鈴木 駿 訳
![[cover photo]](https://www.oreilly.co.jp/books/images/picture_large978-4-8144-0133-8.jpeg)
- TOPICS
- Programming , Python
- 発行年月日
- 2025年10月
- PRINT LENGTH
- 572
- ISBN
- 978-4-8144-0133-8
- 原書
- Effective Python: 125 Specific Ways to Write Better Python, 3rd Edition
- FORMAT
- Print PDF EPUB
目次
はじめに
1章 Pythonicな考え方
項目1 使用するPythonのバージョンを把握する
項目2 PEP 8スタイルガイドに従う
項目3 Pythonがコンパイル時にエラーを検出することを期待しない
項目4 複雑な式ではなくヘルパー関数を定義する
項目5 インデックス参照ではなくアンパックを使う
項目6 単一要素からなるタプルは常に丸括弧で囲む
項目7 単純なインラインロジックには条件式を使う
項目8 代入式で繰り返しを防ぐ
項目9 制御構造をパターンマッチで分割する(ただし、if文で十分な場合は使わない)
2章 文字列とスライス
項目10 bytesとstrの違いを理解する
項目11 Cスタイルフォーマット文字列やstr.formatは使わずにフォーマット済み文字列を使う
項目12 オブジェクト出力におけるreprとstrの違いを理解する
項目13 暗黙的な結合よりも明示的な結合を優先する
項目14 スライスの仕組みを理解する
項目15 同一式でスライスとストライドを一緒に使わない
項目16 スライスではなくcatch-allアンパックを使う
3章 ループとイテレータ
項目17 rangeよりenumerateを優先する
項目18 zipを使ってイテレータを並列に処理する
項目19 forループとwhileループのelseブロックを避ける
項目20 ループが終了した後にループ変数を使わない
項目21 引数をイテレートする際は防御的に行う
項目22 イテレート中にコンテナを変更せず、代わりにコピーやキャッシュを使う
項目23 anyとallで効率的な短絡評価をする
項目24 イテレータとジェネレータを扱う際はitertoolsを検討する
4章 辞書
項目25 辞書の挿入順序に依存する際は注意する
項目26 辞書の欠落したキーにはget()を使う
項目27 内部状態の欠落要素にはsetdefaultではなくdefaultdictで対応する
項目28 _missing__()を使ってキー依存のデフォルト値を生成する
項目29 辞書、リスト、タプルを深くネストする代わりにクラスを定義する
5章 関数
項目30 関数の引数がミュータブルであることを知っておく
項目31 関数の呼び出し元で4つ以上の変数をアンパックせず、専用のオブジェクトを返す
項目32 Noneを返さずに例外を送出する
項目33 クロージャが変数スコープとnonlocalとどのように相互作用するかを理解する
項目34 可変位置引数で可読性を向上させる
項目35 キーワード引数でオプションの動作を付与する
項目36 Noneとdocstringを使って動的なデフォルト引数を指定する
項目37 キーワード専用と位置専用引数で明確さを強調する
項目38 functools.wrapsを使って関数デコレータを定義する
項目39 グルー関数にはlambda式よりfunctools.partialを優先する
6章 内包表記とジェネレータ
項目40 mapやfilterの代わりに内包表記を使う
項目41 内包表記では式を3つ以上使わない
項目42 代入式を使って内包表記の繰り返しを減らす
項目43 リストではなくジェネレータを返す
項目44 大きな内包表記にはジェネレータ式を使う
項目45 yield fromでジェネレータを組み合わせる
項目46 send()を呼び出す代わりにイテレータをジェネレータに渡す
項目47 ジェネレータのthrowメソッドではなくクラスで状態遷移を管理する
7章 クラスとインタフェース
項目48 単純なインタフェースにはクラスではなく関数を使う
項目49 isinstanceよりもポリモーフィズムを優先する
項目50 オブジェクト指向ポリモーフィズムの代わりに関数型シングルディスパッチを検討する
項目51 軽量クラスを定義するためにdataclassesを優先する
項目52 @classmethodポリモーフィズムを使ってオブジェクトをジェネリックに構築する
項目53 superで基底クラスを初期化する
項目54 mix-inクラスで機能を追加する
項目55 プライベート属性よりもパブリック属性を優先する
項目56 イミュータブルオブジェクトを作成するためにdataclassesを優先する
項目57 カスタムコンテナ型はcollections.abcクラスから継承する
8章 メタクラスと属性
項目58 setterおよびgetterメソッドの代わりにパブリック属性を使う
項目59 属性をリファクタリングする代わりに@propertyを使う
項目60 再利用可能な@propertyメソッドのためにディスクリプタを使う
項目61 遅延属性のために__getattr__、__getattribute__、__setattr__を使う
項目62 __init_subclass__による派生クラスの検証
項目63 __init_subclass__によるクラス登録
項目64 _set_name__でクラス属性にアノテーションを付与する
項目65 属性間の関係を考慮したクラス本文の定義順序を考える
項目66 合成可能なクラス拡張のためにメタクラスよりもクラスデコレータを優先する
9章 並行性と並列性
項目67 subprocessでサブプロセスを管理する
項目68 スレッドはブロッキングI/Oのために使う
項目69 Lockを使ってスレッド間のデータ競合を防ぐ
項目70 Queueを使ってスレッド間の作業を調整する
項目71 並行性が必要な状況を認識する
項目72 オンデマンドファンアウト用に新しいスレッドインスタンスを生成しない
項目73 Queueを使った並行性にはリファクタリングが必要であることを理解する
項目74 並行処理にスレッドを使うのであればThreadPoolExecutorを検討する
項目75 コルーチンで高い並行I/Oを実現する
項目76 スレッド化されたI/Oをasyncioに移植する方法を把握する
項目77 スレッドとコルーチンでasyncioへの移行を容易にする
項目78 非同期対応のワーカースレッドでasyncioイベントループの応答性を最大化する
項目79 真の並列処理にはconcurrent.futuresを検討する
10章 ロバストネス
項目80 try/except/else/finallyブロックを使う
項目81 assertで前提条件を検証して、raiseで予想外の事象を通知する
項目82 contextlibとwith文で再利用可能なtry/finallyの振る舞いを実現する
項目83 tryブロックを可能な限り短く保つ
項目84 例外変数が消失することに注意する
項目85 注意してExceptionクラスを捕捉する
項目86 ExceptionとBaseExceptionの違いを理解する
項目87 tracebackによる高度な例外報告
項目88 例外を明示的に連鎖させてトレースバックを明確にする
項目89 ジェネレータには常にリソースを渡し、呼び出し元でクリーンアップする
項目90 __debug__をFalseにしない
項目91 開発者ツールを実装する場合を除いてexecとevalを使わない
11章 パフォーマンス
項目92 最適化前にプロファイリングを行う
項目93 timeitを使ってパフォーマンスが重要なコードを最適化する
項目94 Pythonを別のプログラミング言語に置き換えるタイミングと方法を知る
項目95 ctypesでネイティブライブラリと迅速に統合する
項目96 拡張モジュールでパフォーマンスと利便性を高める
項目97 コンパイル済みバイトコードとキャッシュで起動時間を短縮する
項目98 動的インポートによるモジュールの遅延読み込みで起動時間を削減する
項目99 ゼロコピー処理のためにmemoryviewとbytearrayを使う
12章 データ構造とアルゴリズム
項目100 keyパラメータによる複雑なソート
項目101 sort()とsorted()の違いを理解する
項目102 ソート済みシーケンスにはbisectを使う
項目103 プロデューサ・コンシューマキューにはdequeを使う
項目104 優先度付きキューとしてheapqを使う
項目105 datetimeを使ってローカル時刻を扱う
項目106 精度が極めて重要な場合はdecimalを使う
項目107 copyregでpickleを管理する
13章 テストとデバッグ
項目108 TestCaseでテストを実装する
項目109 ユニットテストよりも統合テストを優先する
項目110 setUp、tearDown、setUpModule、tearDownModuleでテストを互いに分離する
項目111 複雑な依存関係はモックする
項目112 依存関係をカプセル化してモックとテストを容易にする
項目113 浮動小数点数のテストではassertAlmostEqualを使う
項目114 pdbによるインタラクティブデバッグ
項目115 tracemallocを使ってメモリ使用量とメモリリークを把握する
14章 コラボレーション
項目116 サードパーティライブラリの探し方
項目117 仮想環境を使う
項目118 必ずdocstringを書く
項目119 パッケージでモジュールを整理して、安定したAPIを提供する
項目120 実行環境に合わせてモジュールを調整する
項目121 APIの基底例外を定義してAPIから呼び出し元を分離する
項目122 循環インポートを解消する
項目123 warningsでリファクタリングや移行を促進する
項目124 静的型解析でバグを回避する
項目125 Pythonプログラムのバンドルにはオープンソースツールを検討する
訳者あとがき
索引